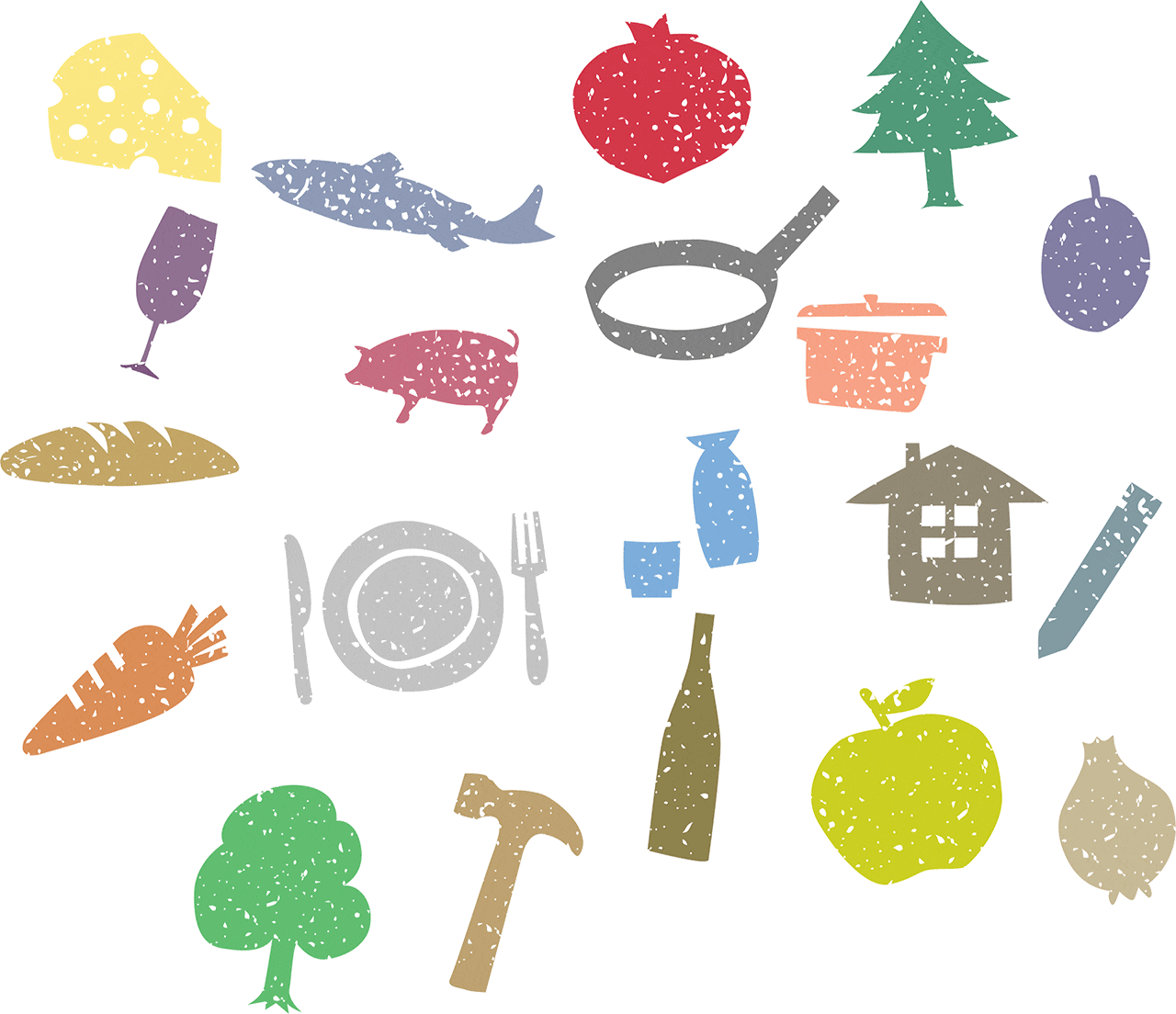自分が表現したいものが投影できたらもっといい
ネモファニチャーは家具職人の荻原敬さんがひとりでデザイン、制作を担当する家具工房。2005年に設立された。
荻原さんと家具の思い出は子供の頃に遡る。実家にあった民芸家具のサイドボード。他の家具とは何もかもが違っていた。手触りも、見た目も、ひときわカッコ良くて、ガラス扉を開けるときはいつもドキドキした。もちろん本当の価値など知る由もなかったけれど、それが初めて知った“何かが違う”ことへの肌感だった。
「家具が好きだったかと聞かれたら、好きだったのかもしれない。でも絶対に家具職人になりたいと思っていたわけでもないんだよね」
そう話す荻原さんは、以前は現場監督として道路や橋、大きな建物を造ったりしていたそうだ。
しかし土木の世界では、機能や安全性が最も大切で美観は二の次、という考え方をすることが多く、荻原さんは少しずつそこに物足りなさを感じ始める。しかも現場が大きくなればなるほど、自分が関わる仕事はごく一部だ。大勢の人がひとつのものを造るのだからそれは仕方がないが、自分が最初から最後まで責任を持ってやり遂げる仕事がしたい、そこに自分が表現したいものが投影できたらもっといい、と思うようになった。
そうして選んだ道が、家具職人だった。
学校に通い家具作りの基礎を学んだら、すぐに独立しようと思っていたと荻原さんは言う。
「学校にいたときは内面のエネルギーがとにかく強くて、自分の好きなものだけ作れたらそれでいいと思っていたんです」
そんな時、学校の先生に、お客様のニーズに応える仕事も必要だ、という言葉をかけてもらい軽井沢の家具工場に勤めることを選択。結果的にそこでは学校で学んだ以外のことを多く学ぶことができたと振り返る。

家具職人として生きていく上で、お客様の声を反映する重要性を実感するようになった。
「先生は、自分の作りたいものだけを作って消えていったたくさんの教え子を見てきたんでしょうね。僕がそうならないように、お客様が求めるものを作る必要性を教えてくれたんだと思います」
先生からもらった言葉は、ネモファニチャーとして工房を立ち上げてからも荻原さんを支えたが、家具職人として多忙を極めるようになったとき、ふと自分が作りたいものが作れなくなっていることに気づいたという。
「そうなると、自分の好きなものが作りたいって強く思うんですよね。何年も、誰かのニーズに応えることと、自分の好きなものを作ることの間で行ったり来たりしていたように思います」
“好きなものを作る”ことは、自身を表現することと同意だと話す。
思えば子供の頃から、言葉以外の方法で自分の気持ちを表すことが好きだった。
小さい頃は絵を描くこと。
大学時代は音楽。
それが今は家具に変わった。
「芸術が活かせる物質的なものに、僕はいつも振り回されているんですよ」と荻原さんはどこか嬉しそうに笑った。
いつかそれが基準になっていく
現在、ウェブサイトにはスタンダードというカテゴリーがある。
そこには「家具に対する哲学、価値観、美的感性を投影した、基本にして最良のシリーズ」と書いてあり、荻原さんが家具を作り続けていく中でたどり着いたネモファニチャーの“土台”とも言える。スタンダードラインの家具は、テーブルや椅子、ソファなどの生活用品であり、置く場所を選ばず、どんなシチュエーションにも馴染むものたちだ。自身の感性を投入しつつ、何十年経っても色褪せないデザインを追求することで、受け皿はぐんと広くなった。品質のよさはもちろん、世代を超えて使い続けられる丈夫さも持ち合わせている。
 その一方で、荻原敬個人としても作品を作りはじめた。それらは荻原さんの自由な発想で、またその時々の作りたいものを形にするもの。ネモファニチャーの家具とは似て非なるものだ。それらの作品は現品販売で、いつ、どんな時期に何が生まれるのかは分からない。そしてその価値を決めるのも購入してくれる人々に委ねたいのだという。
その一方で、荻原敬個人としても作品を作りはじめた。それらは荻原さんの自由な発想で、またその時々の作りたいものを形にするもの。ネモファニチャーの家具とは似て非なるものだ。それらの作品は現品販売で、いつ、どんな時期に何が生まれるのかは分からない。そしてその価値を決めるのも購入してくれる人々に委ねたいのだという。
またスタンダードラインのほとんどはアメリカ産のウォルナットだけで作られているのに対し、作品を作るときの種材は自由だ。時には複数の種材を混ぜて使うこともあるし、材木屋さんから買えるものは何でも使う。
どちらも荻原さんの“好きなもの”には変わりはないけれど、計算され尽くして生まれたスタンダードと、その時の感情をリアルタイムに乗せて作る作品とでは、見た目も趣旨も、出来上がるものも大きく変わる。
これからはこのふたつを両立させて、家具職人として邁進していくと教えてくれた。

新しいことをやろうとすると、それが突飛であればあるほど受け入れられないことが多い。でもたとえゆっくりでも、それを面白がってくれる人たちが増えれば、いつかそれが基準になっていく。この世の中に根付いている「ふつう」はいつもそんなふうに生まれてきた。
もしかしたら今後、荻原敬個人として作った家具たちが、ネモファニチャーのスタンダードラインの仲間入りをする日が来るのかもしれない。そんな日が、今からとても楽しみだ。